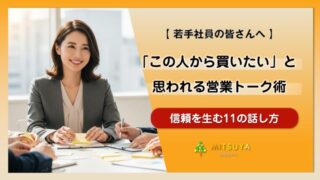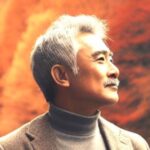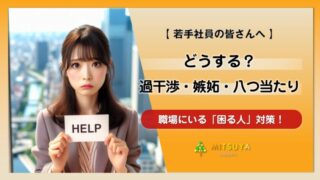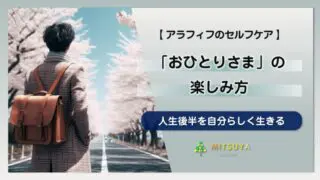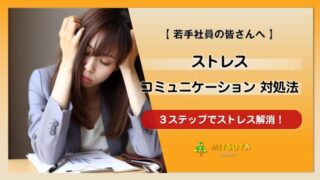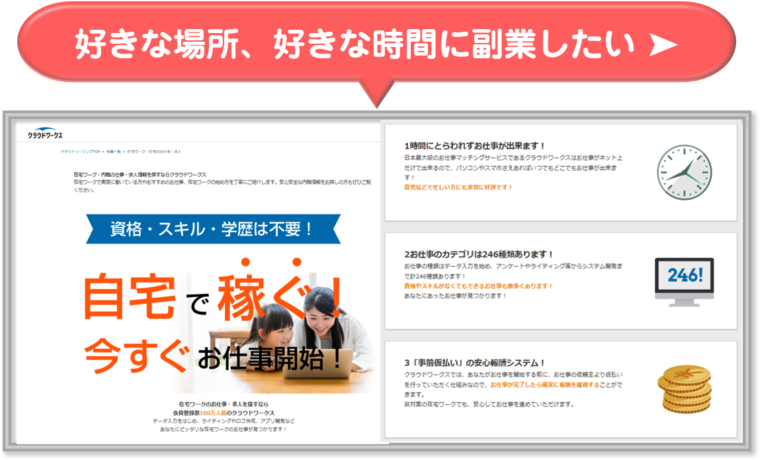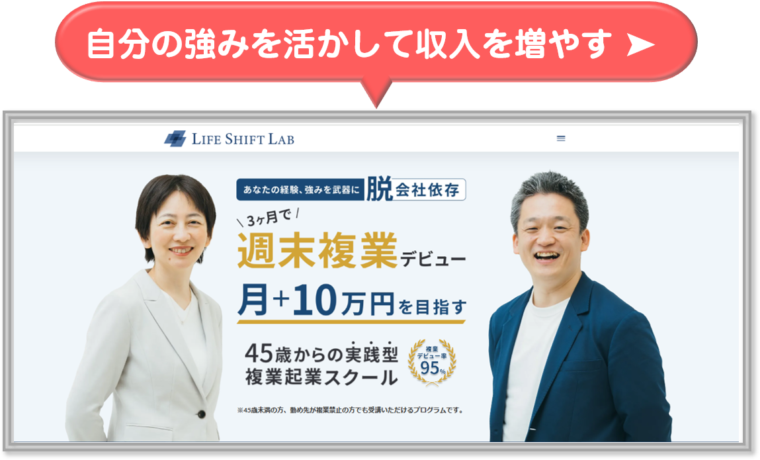「指示待ち部下」を変えたい:自走力を育てる『伴走型マネジメント』のすすめ
指示しないと動かないし…
自分で考えようとしない
多くのリーダーが抱えるこの悩みは、いまや個人やチームの問題にとどまりません。
内閣府 「国民生活に関する世論調査」によると…
「お金を得るために働く」と答えた人の割合は2014年以降増え続け、2023年には64.5%に達しています。
一方で、「生きがいを見つけるために働く」と回答した人は2001年の24.4%から12.8%へと半減。

この傾向は、単に金銭志向が強まったというよりも、「働くことに充実感を求める意識そのものが弱まっている」ことを示しています。
博報堂はこれを「働く」の低温化と呼びました。
仕事への熱量が低下すれば…
責めを負うくらいなら
動かないほうがいい
そんな「静かなブレーキ」をかけてしまいがち。
こうした中、注目されているのが…
「伴走型マネジメント」
という考え方です
「お手本型」から、寄り添いながら共に成長を促す「伴走型」へシフトすることで、部下が自ら考え、動き、成長するチームへと変化していきます。

なぜ今、『伴走型マネジメント』なのか

これまでのマネジメントは…
「上司が正解をもっていて、それを教える」スタイルが中心でした。
いわば…
お手本型マネジメント
この方法は変化が少なく、効率が重視された時代には有効でした。
しかし今は、状況がまるで違います。
正解が一つではない中で、上司がすべてを判断するやり方には限界があります。
リーダーがすべてを決めるほど…
部下は「考える前に確認する」「言われるまで待つ」ようになっていきます。
結果…
リーダーは疲弊し
部下は育たない…
そんな悪循環が、あちこちの現場で起きています。
そこで、いま求められているのが、部下の自律的な成長を支える「伴走型マネジメント」です。
「伴走型マネジメント」とは…
部下の目標に向かって隣で並走し、自ら考え行動する力を支援するスタイルのこと
リーダーがすべての答えを与えるのではなく、部下が「自分の頭で考え」「行動の意味を見出せるように支援する」関わり方です。
その結果、部下の自走力とチームの成果を同時に高めることを目指します。
ティーチング、コーチングとの違いは…
| アプローチ | 目 的 | 関わり方の特徴 |
| ティーチング | 知識やスキルの伝達 | 答えを教える |
| コーチング | 自発的な気づき | 質問で考えを引き出す |
| 伴走型マネジメント | 自走力の育成 | 状況や成長段階に応じて、教え・問い・支援を柔軟に使い分ける |
教える・問う・支援するを
状況に応じて使い分ける
これが伴走型の特徴。

経験が浅い部下には「教える」ことで基礎をつくり、 少しずつ自走できるようになったら「問いかけ」で考えを引き出します。
たとえば…
なぜそう考えた?
どんな方法がありそう?
…といった問いを投げかけながら、思考の整理をサポートします。
考えるプロセスを一緒に歩みながら…
部下の、自分の言葉で考え、判断する力を育てていきます。
安全に挑戦できる環境をつくる:心理的安全性とリカバリーの両立

どんなに優れたマネジメント理論も、信頼関係がなければ機能しません。
部下が本音を話せず、失敗を恐れて動けない状態では、伴走も成立しない。
たとえば会議、上司の顔色をうかがい
… シーン
1on1で「習得したいスキルや経験はありますか?」と聞いても、
特にありません … シーン
こんな「シーン」に遭遇すること、ありませんか?
部下の心中は…
失言、失敗を指摘されるくらいなら、無難な対応で
波風立てずに済ませたい
つまり…
波風を立ててまでリスクを取ろうとは思わない、という状態です。
「安心」の担保がない限り、個人やチーム全体に心理的なブレーキは解除されません。
そこで、まず大切になるのが信頼関係の醸成です。

具体的には、次の3点がポイントになります。
- 一貫性のある態度
「感情習慣」を意識し、日々の言動を安定させる - 相手の話を受け止める姿勢
評価や指摘を返さず、まずは受け止める - 失敗を成長につなげる視点
「次にどう活かすか」を一緒に考える
上記の「感情習慣」については、以下の記事で解説しています。
リーダー必須の内面的スキルとして、ぜひご活用ください。
さらに…
部下が安心して挑戦できるよう、リカバリーやフォロー体制を整えることもリーダーの仕事です。
心理的安全性とは、単なる失敗の容認ではなく、未知の領域や複雑な課題に安心して挑戦できる環境を指します。
タイプ別に見る!自走力を引き出す関わり方


自走力を育てる基本ステップは、
① 聴く② 問いかける ③プロセスを評価する
しかし部下によって響く「入り口」は異なります。
そこで有効なのが、心理学(認知行動療法)の考え方を応用した…
「行動・思考・感情」の
3タイプ別アプローチ


具体的には…
わたしは 行動タイプ
結果志向で実行力がある。
明確な指示や目標があると動きやすい。
アプローチのポイント
- 「〇〇を〇日までに、こういう方法で」と具体的に伝える
- SMART原則に沿った目標設定
- 行動の承認と具体的な改善フィードバック
- 行動が止まったら、背景の思考や感情を確認
わたしは 思考タイプ
論理的・分析的で、納得感を重視。
「なぜそうするのか」「どういう意味があるのか」を理解して動く。
アプローチのポイント
- 決定の背景や目的を説明
- 意見を求める対話
- 原因・対策を整理
- 別の視点を提示して思考の幅を広げる
わたしは 感情タイプ
共感や安心感を重視し、人間関係や雰囲気に敏感。
まずは気持ちに寄り添い、受け止める姿勢が大切になります。
アプローチのポイント
- 「そう感じたんだね」と受け止める
- 安心して話せる雰囲気づくり
- 感情の言語化を促す
- 達成や感謝を共有してモチベーション向上
この「感情タイプ」には「アクノレッジメント」のコーチングがとても有効です。
以下の記事で解説していますので、ご活用ください。
大切なのは…
部下のタイプの見極めです。
おススメは…
1on1などの対話の場で、部下の反応の違いからタイプを判断する方法。
たとえば、行動タイプ…
A部門の承認が止まっています
上司からプッシュしてもらえますか?
→ 具体的な支援を求める
思考タイプ…
この問題の解決策を
一緒に考えてもらえますか?
→ 考えを整理したい
感情タイプ…
最近
プレッシャーを感じていて…
→ 気持ちを理解してほしい
部下がどんなサポートを求めているかで、心に届く「窓口」は見えてきます。
その入り口に合わせて声をかける…
それが、部下の自走力を引き出す最大のポイントです。
「共感型」のコミュニケーションスキルについては、以下の記事が参考になります。
ご活用ください。
伴走型リーダーが生み出す好循環

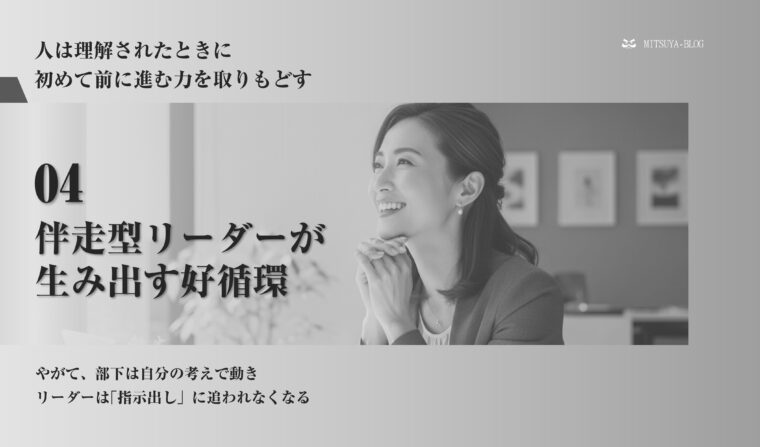
伴走型マネジメントは、単に「やさしい関わり方」ではありません。
部下をよく観察し、その人のタイプや状況に応じて関わり方を変える…
その積み重ねによって、部下の自走力が育ちます。
- 行動タイプには、次の一歩を一緒に考える
- 思考タイプには、考えを整理する対話をする
- 感情タイプには、まず気持ちを受け止める
リーダーがこうした「入り口」を意識するだけで、部下の反応は驚くほど変わります。
人は理解されたときに、初めて前に進む力を取りもどすからです。
やがて、部下は自分の考えで動き…
リーダーは
「指示出し」に追われなくなる
結果…
チームに信頼と前進のリズムが生まれます。
伴走とは…
部下一人ひとりの歩幅を見極め、ときに支え、ときに任せ、ともに走ること
ときには、部下に学ぶ姿勢も…
それが、チームを自走へと導く確かなマネジメントです。
まずは…
1on1で、こんな問いかけから始めてみましょう。
社内で「理想的だな」
と思う人を挙げるとしたら誰ですか?
その理由を尋ねた時…
部下が理想の社員の、行動に着目しているか・考え方に惹かれているのか・人柄を真似たいのかで、社員のタイプが見えてきます。
そして…
部下の「入り口」に合わせて対話を深める。
それが、部下の自走力を育て、チーム全体に成果と信頼の好循環を生み出すカギとなります。
なお…
「好感度」を上げるコミュニケーションについては、以下の記事で解説しています。ご活用ください。