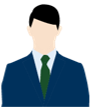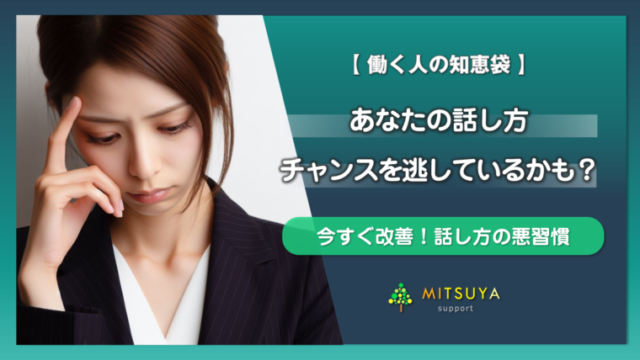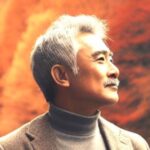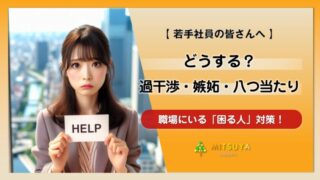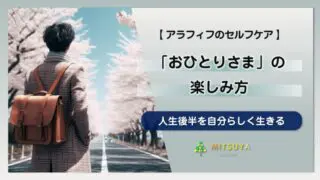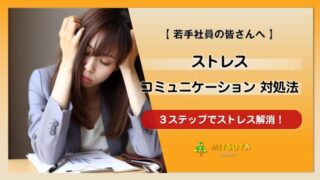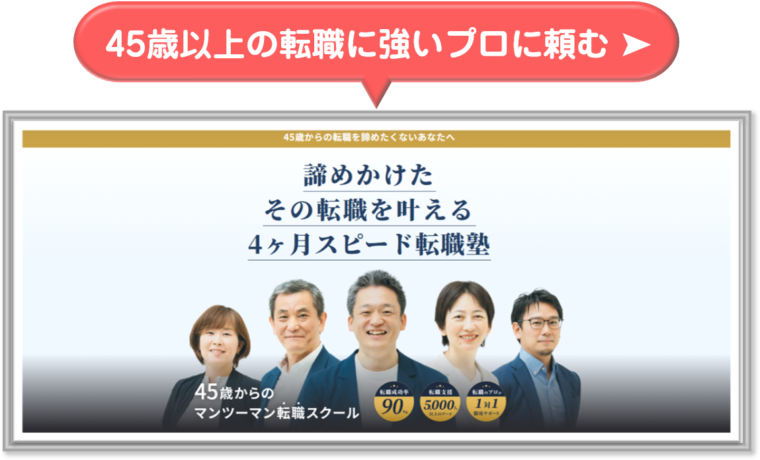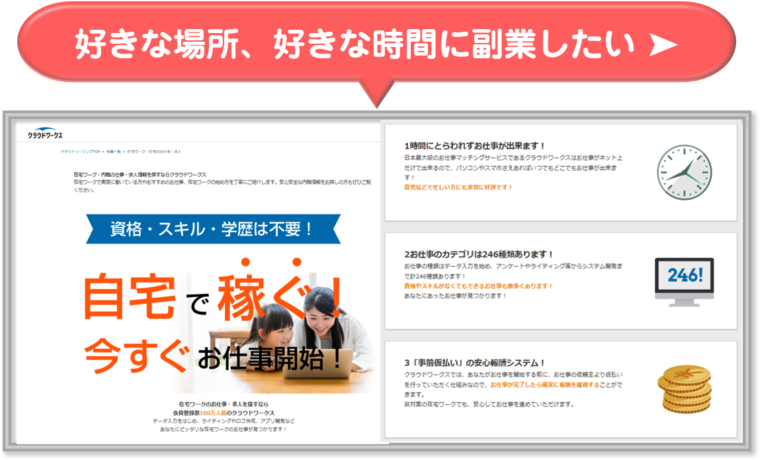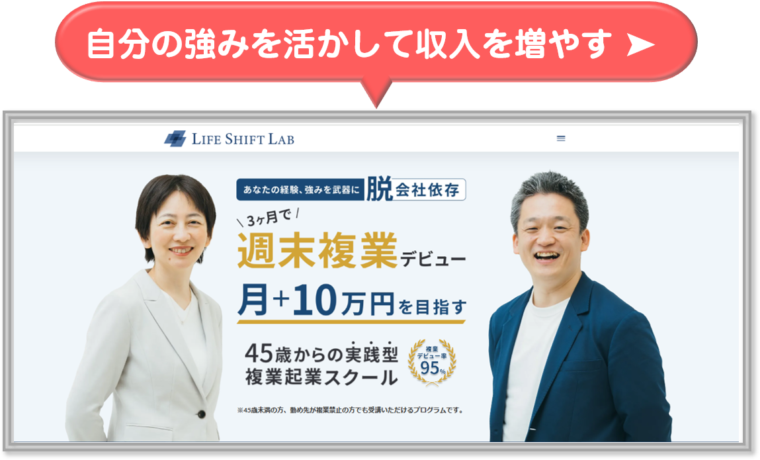なぜか、社員の反感を買ってしまう…
という方は、伝え方のコツをつかめば改善できます。
たとえば、新年度のスタート。
チーム編成が変わったり、新規事業が発足したりすれば…改めて会社や自身の方針を社員に浸透させなければならない。
直面するのは、あなたが社員に求める「行動変容と実態とのギャップ」です。
このギャップを埋めていきながら、順調なスタートを切りたいところ…
気がかりなのが、社員の抵抗や反感です。
そんなマネジャーを助けてくれるのが…
主体を変換する「伝え方の技術」
マネジャーのみな様のストレスの軽減を目標に、本記事では…
伝え方の技術を解説
具体的には、次の3点です。
こんな方・こんな状況に役立ちます。
- 社員の行動変容を円滑に進めたい
- 自分の部署に、あなたに反感をもつ部下がいる
- 目標達成のために、組織の主体性を高めたい
- あなたが求める行動変容が組織に浸透しない状況にある
簡単に内容を知りたい方は Instagramへどうぞ…
https://www.instagram.com/mitsuya_biz
伝え方の技術3選: 選択肢の提供・質問の活用・ギャップの明確化

これより紹介するテクニックは…
『THE CATALYST』(ジョーナ・バーガー:ペンシルバニア大学校教授)の中で提唱されたメソッドの、ビジネスへの応用になります。
部下に行動変容を促したが、反発を招いた…などの危機からあなたを救うテクニックです。
内容は次の3点…
人間の心の働きの中には、「選択の自由を脅かされたときに生じる、自由を取り戻そうとする反発作用」があります。
「心理的リアクタンス」(心理学の用語)という現象です。
人の影響を受けたくない、自分の自由意思で決めたいという強い欲求が作用しています。
ビジネスシーンで起こりやすいのは…
- 年度初めに新たな方針や行動目標を示すとき
- 新入社員に自社の慣例・慣行を伝えるとき
- 異動先の部署で、部下に自分の方針を示すとき
本記事の内容は、これらの場面で役立ちます。
伝え方の技術を解説:3つのテクニック
❶ 選択肢を提供する
ビジネスとは利益の最大化を目指す営み。
口悪く表現すれば、リーダーの役割とは…
利益創出に向けて、個人や組織を「誘導」することです。
この誘導テクニックが「メニューの選択」
具体的には、以下の手順になります。

「事実」を示したのち、「方策」「プロセス」に関する選択肢を社員に提供し、目的地まで誘導するという流れ。
選択肢を検討させることにより、社員を意思決定の主体へと変換します。(主体の変換)
ポイントは準備です。
具体的には次の2点…
- 行動変容の必要性を喚起するデータを精選すること
- どれを選んでもあなたの目的を達成できる選択肢を用意すること
自分たちが主導権を握っていると感じさせることが目標です。
このことにより、「押しつけられた感」を防ぐことができます。
❷ 命令ではなく質問をする
「メニューの選択」に同じく、「質問」にも意思決定の主体を提案側から受け手に変換する効果があります。
原理としては…
人は他人の考えには従いたくないが、自分で考えたことなら従う…
という考え方に基づきます。
次の2つの例を比べてください…
今回のプロジェクトは、チーム内の情報の共有がカギだ。
横の連携を密にするように!
今回のプロジェクトは、チーム内の情報の共有がカギだ。
横の連携を密にするためには、いつ、どのように社員間で接点をもつとよいだろう?
「×悪い例」は、指示・命令。
「◎良い例」は、意思決定の主体を相手にゆだねています。
意思決定を「ゆだねる」ことにより、社員は結論を出したのは「私(たち)」だという自覚をもちます。個人の責任が発生するとともに、上司が認めることにより共同責任が生まれる。
ポイントは…
目的を示し、考える範囲を限定すること
そうすることで、意図する目的から外れません。
良い例の「横の連携を密にするため」の部分です。
質問を使うと、社員から多くのアイデアが出ることが期待できます。
予想を超える良い解決策を生む可能性も広がる。
コーチングにおいても質問は重視されます。
質問によって「行動と学習」の主体を相手側に置くことができるからです。
主体を相手側に置くことで、自発的なアクションを促すことができます。
反感を招く上司は、A係長のように指示・命令に偏った伝え方になっている場合が多い。
命令を質問に代えるだけで、印象が大きく変わります。
「質問の活用」については、以下の記事でも取りあげています。ご参照ください…
❸ ギャップを明確にする
ギャップを明確にするとは…
他人に言うことと、自分がしていることの矛盾を本人に気づかせる…ということ
人間は首尾一貫していることを求める習性があります。
自分の態度と価値観に矛盾が生じると落ち着かない気分になります。
先ほどの例で言いますと…
今回のプロジェクトは、チーム内の情報の共有がカギだ。
横の連携を密にするためには、いつ、どのように社員間で接点をもつとよいだろう?
に対して組織内で次の案を採用したとします。
出社した時点で、連携をとる社員に伝達します。
翌日直行の場合は、メールでメモを残します。
ところが、C社員自身が連携をおろそかにしている、と耳にした。そこで…
君の案で、うちの部署の連携方法について確認したが…
その後、確実に実行できているかね?
と気づきを促します。
この場合も「質問」を用います。
以下のコーチングモデルの記事や、先に示した質問力の記事を参照すると、よいアイデアが浮かびます。ご参照ください。
「ギャップを明確にする」方法は、行動変容の定着を図りたい場面で有効に働きます。
上司と部下との関係性の悪化は人的資源の喪失をもたらす


上司と部下の関係性の悪化は人的資源の喪失につながります。
以下の記事に、「上司と部下」の意識調査・「嫌いな上司」に関する調査結果を載せております。
上司との関係がうまくいかず、部下が離職という事態は避けたいところ。
注意が必要なのは、自身の伝え方の習慣や癖です。関係悪化の要因は、気づきにくいところにあるからです。
本記事を自己チェックにお役立てください。
今後の生活資金に対する不安、健康不安、急な出費への備え…
そんな不安を安心に変える方法を以下の記事にまとめました。
キャリアアップを目指しながら副収入もほしい…という人向けの記事です。