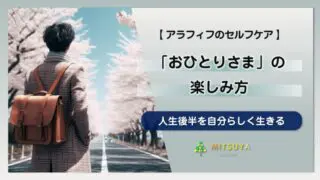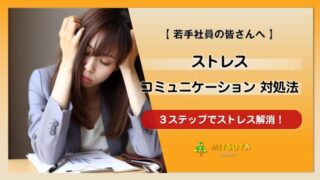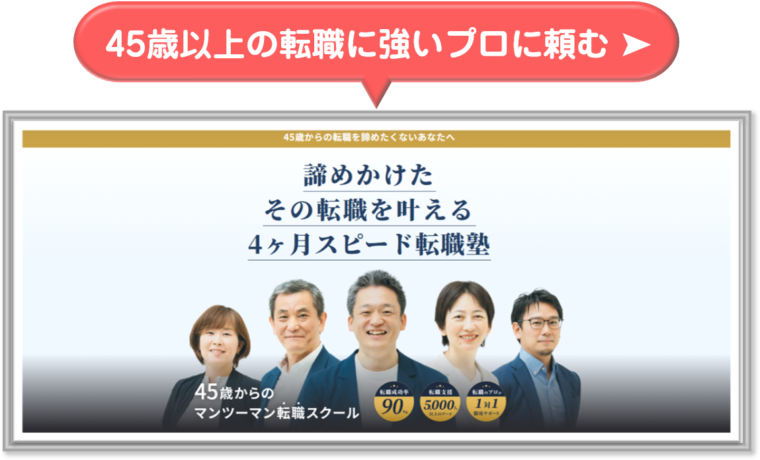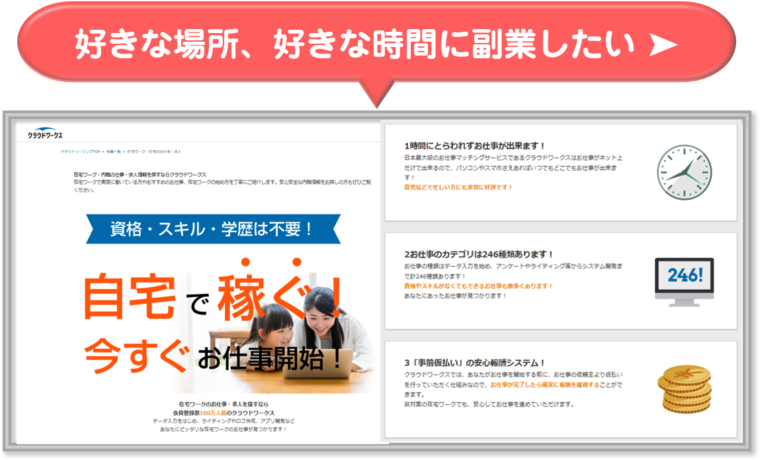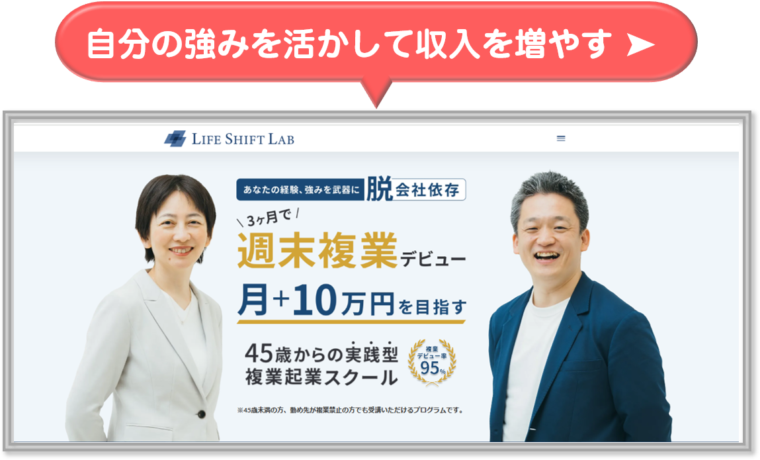京都の旅と言えば、アラフィフはこのキャッチコピーを思い出します。
東京出張の帰り、帰福を一日延ばして半日京都の旅にあてることにしました。
結果、「錦秋」にはやや早く、11月下旬にかけて見ごろが続くであろうと思われ…
これより京都を旅する方に間に合うよう、あわてて記事にした次第です。
そうだ 京都 行こう
と思い立った方にお役に立てば幸いです。
お忙しい方は雪景色の京都…
いかがでしょうか。
まずは、「庭園景と癒しの深い関係」について解説し、短い京都の旅を紹介。
簡単に内容を知りたい方は Instagramへどうぞ…
https://www.instagram.com/mitsuya_biz
庭園景と癒しの深い関係:原風景が癒しをもたらす

2022.11.12 大河内山荘の庭園 撮影:MITSUYA
今回は半日の短い旅。
そこで、タクシーをチャーターしました。
併せて、ベテランのドライバーを依頼。
お世話になったのは、運転歴&ガイド45年のベテランドライバー:トクさん(仮名)。
御年67歳。
京都の見どころを、やや漠然と尋ねたところ…
トクさん、「庭です」と即答される。
庭あってこそ、四季を楽しむことができ、安らぎや癒しをもたらす…
という持論を展開。
トクさんの言われるとおり、庭園景と癒しには深い関係があります。
「庭園景から受ける癒しのイメージに関する調査研究」の要点を4つに整理すると…
- 被験者が庭園景から受ける癒しを規定していた基本因子は情趣性・自然性・清澄性。
- 庭園景に対する、好きと癒されるという感情はほぼ同じ。
- 被験者が癒しを感じる庭園景は特に苔や水のある、湿った印象の強い坪庭 露地 日本庭園など日本独特の景観。
- ヒアリング調査の結果から、特定景観に癒しを感じる理由として原風景が強く影響しているものと考察。
『東京農業大学農学集報』48(3), 115-127, 2003-12
https://agriknowledge.affrc.go.jp/RN/2030683643.pdf
※被験者30名(東京農業大学地域環境科学部造園科学科の学生)による調査
癒しをもたらす庭とは…
「原風景を思い起こさせる庭」というわけです。
人が手を加えて「原風景」を庭空間に表現したのが「庭園」
京都は千年かけて、
庭空間に原風景を描き続けてきた。
トクさん曰く…
嵐山も一つの庭なんですわ…
手間ひまかけて造った庭なんです。
京都以外に、嵐山はできしません。
京都の景観に心惹かれるのは、内なる原風景が共鳴を起こしているからでしょうか。
不思議なことは…
アドバイザー
「内なる原風景」を
時間や空間を超えて、私たちが共有していることですね。
京都ガイド【南禅寺】後ろに山がないと、景色が抜けてしまうんですわ

2022 11.12 正面より 撮影:MITSUYA
さっそく、トクさんの京都ガイドが始まる。
まず、南禅寺三門越しの景観を指して…
ここからの景色、いかがですか…
方丈の向こうに山がありますやろ。
山が必要なんです。
後ろに山がないと、景色が抜けてしまうんですわ。
奈良と京都の雰囲気の違いは、ここにあるかもしれない。
円通寺や修学院離宮など、京都は比叡山を借景としてとり入れた庭が多い。
山の役割と言えば借景しか思い浮かばないが…
どうもそれだけではないらしい。
山を背負わないと…
「景色が抜けてしまう」というトクさんの解説。
この視点をもち、改めて京都の庭を味わっていこうと思う。

2022.11.12 法堂から見た三門 撮影:MITSUYA
「絶景かな、絶景かな」という石川五右衛門のセリフまわしで有名な南禅寺三門。
目前の三門は、藤堂高虎の再建によるもの。
国宝「方丈」は回らず、水路閣を見上げに行きます。

2022 11.12 水楼閣 撮影:MITSUYA
曲線美を描く赤レンガのアーチ。
風雨に耐える古城を連想させます。
紅葉越しの水路閣の風情にしばし見とれる。
下の写真は、水路閣を上から見た様子。
現役の水路です。

近くに日本で最初の事業水力発電所:蹴上発電所(現役)があります。
明治時代、ここから受電して市内の電車を走らせたとのこと。

京都ガイド【将軍塚青龍殿】絵心のない庭師はあきまへん

2022 11.12 陶器でできた額 撮影:MITSUYA

2022.11.12 撮影:MITSUYA
今日は空がええから…
青龍殿の大舞台からの景色がすばらしいと思います。
トクさんの提案で、山上まで車を走らせました。
着いた大舞台からの眺めは…

2022.11.12 撮影:MITSUYA
展望台から動画を撮りましたので、併せて紹介…
トクさんの案内により庭園を散策。
トクさんの「庭語り」が続きます。
最初にトクさんが足を止めたのは、くぐり門の前。

2022.11.12 撮影:MITSUYA
庇の後ろから空を入れないように庭を見てごらんなさい。
絵になりますやろ。
庇で空を切るんですわ。
空を景色に入れたら、
光が消えて「しまり」がなくなります。
空を切って見る景色が絵になるかどうか…
これで庭師の腕がわかります。
絵心のない庭師はあきまへん。
奥のほう、見てください。
わかりますか?
わざと道を曲げとるんです。
道を曲げることで奥行きを出してます。

2022.11.12 撮影:MITSUYA
垣(かき)をつかって、
横線を入れとるんです。
横線を入れんと、
景色がのっぺらぼうになるんですわ。
トクさんが指さしたのは、下の写真の四ツ目垣。
「垣」が庭の空間美に一役買っているとのことです。

2022.11.12 撮影:MITSUYA
トクさんの庭ガイドのおかげで、
庭の楽しみ方や庭師の工夫が見えてきました。

京都ガイド【大河内山荘】皆さん、ふり返ることを忘れてます

2022.11.12 撮影:MITSUYA
次は、こちらのリクエストで、大河内山荘へ。
大河内山荘は、時代劇の名優 大河内傅次郎が、小倉山につくりあげた庭園。
大河内傅次郎は福岡県豊前市出身。
九州人の京都へのあこがれやイメージがこの庭に映し出されている感じがして…
京都に来たら、いつもここに立ち寄ります。

2022.11.12 撮影:MITSUYA
大河内山荘の庭は回遊式。
引き続き、トクさんの「庭語り」で庭園を紹介。
ここで、止まって後ろをご覧ください。
ふり返ると、下の景観が目前にありました・・・

2022.11.12 撮影:MITSUYA
ええでしょう?
順路の矢印があるもんで、
皆さん、前へ前へと歩きなはる。
ふり返ることを忘れてます。
足を止めて見る、ふり返って見る、
そうやって庭を楽しんでください。
トクさんの言われるとおり、ふり返って見る庭景色も味わい深い。
庭景色が歩んできた人生と重なり、しばし足が止まる。
その後、お抹茶をゆっくりいただき、大河内山荘を後にしました。

京都ガイド【山椒鶏みそうどん・あぶり餠】京都の味を楽しむ
駆け足で回った秋の京都ですが、トクさんの紹介により京都の味も楽しめました。

西尾八ッ橋の里(西尾八ッ橋別邸)
電話:075-752-2188
住所:京都市左京区 聖護院西町6
営業時間変更:11時~15時 / L.O. 14時半(当面の間)
定休日:月曜日(当面の間)*祝日は営業
https://www.8284.co.jp/shop/8284nosato.html
山椒鶏みそうどん 2022.11.12
豊かな山椒の香りが、食べ終わりまで絶えずに残ります。
コシのある細麺、コクのあるスープ。
箸の止まらぬ美味しさ。


一和(いちわ)
京都府京都市北区紫野今宮町96(南側)
電話 075-492-6852
営業時間 10時~17時
定休日 水曜日
一和のあぶり餠 2022.11.12
今宮神社の名物あぶり餅です。
焦げ目がついたお餅を特製白みそだれを絡めていただく。
創業は平安時代(天保2年/1000年)。
古(いにしえ)の味そのままを頬張る。

日常から離れ…
「自由な時間と空間を手に入れたい」という人は、以下の特集をご覧ください。
桜の咲くころに、また「京都、行こう」
これまで、知覧を3回ほど訪れました。

知覧武家屋敷庭園 有限責任事業組合(公式ホームページ)より
知覧に残る武家屋敷の庭は、亭主が楽しむ目的で造られたものです。
したがって、その家の主(あるじ)の世界観が庭に反映し、必然的に個性豊かなものができあがる。
おそらく、主が気に入らなければ、庭師に「ああせい、こうせい」と自分好みに変えていったと思われます。
一つ間違えば腹を召さねばならぬ「お勤め」から家に帰り、庭と対面する。
安らぎか、覚悟か、安息か、決意か、
その時々の思いによって、主の目には庭が違って見えたことでしょう。
目覚めて見渡す、勤めから帰って相対する、石灯籠に火をともして風情に浸る、月あかりに浮かぶ庭を愛でるなど、楽しみ方は様々だった。
これに対し、京都の庭は人に見せることを前提に造られてきたと言えます。

2022.11.12 撮影:MITSUYA
寺社であれば高貴な方もお参りに来られる。
参拝後、主が庭に面した部屋に賓客を招き、お茶を出してもてなす。
庭も話題の一つだったと思われます。
おそらく、「先日見た庭はビミョーだったが、おたくの庭はイケてる」などと、本心か空世辞かわからぬ会話もあったことでしょう。
流行もあったでしょうし、評判が立てば多くの人が訪れた。
必然的に、美意識の高い都人の目にかなう庭がつくられ、残されていく。
そうやって、千年かけて庭を磨き上げてきた。
今回は、そうした京都の庭を楽しむ機会を得ました。ベランダもない団地育ちの筆者にとって、庭園はまぶしい存在。
桜の咲くころ、また訪れたい。
そのときは、またトクさんのお世話になります。
順路の矢印があるもんで、
皆さん、前へ前へと歩きなはる。
ふり返ることを忘れてます。
足を止めて見る、ふり返って見る、
そうやって庭を楽しんでください。
トクさんの「庭語り」が人生の歩みと重なり、心にしみました。
近ごろは歯を食いしばって仕事することも多く…
前回の久住の旅とともに、京都の旅は「足を止める」いい機会になりました。
では、皆様、よきトラベルライフを!
京都のお庭ガイドの動画を紹介しておきます…
大切な方に「旅行」をプレゼントしたい人には…
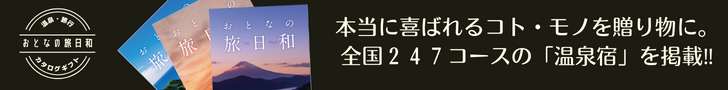
京都一人旅の関連書籍を紹介…