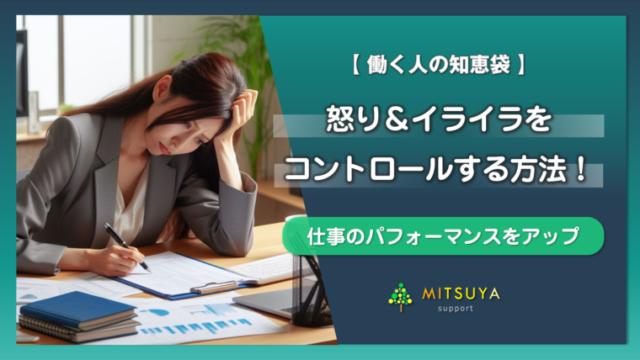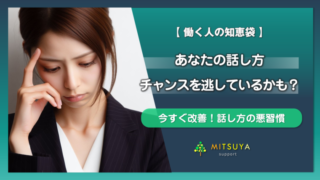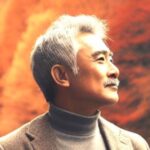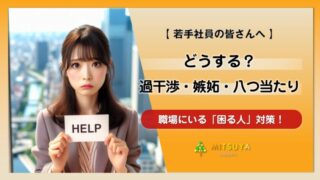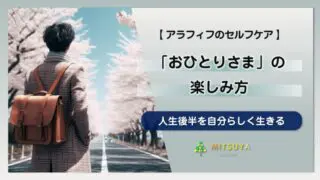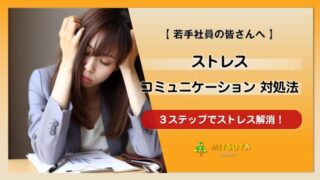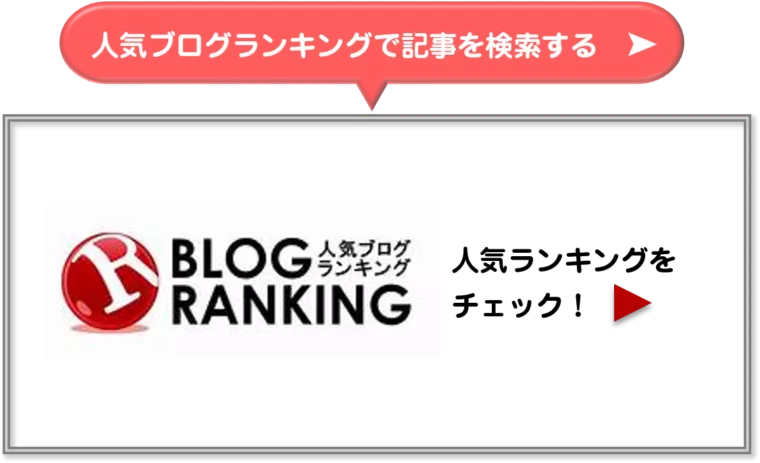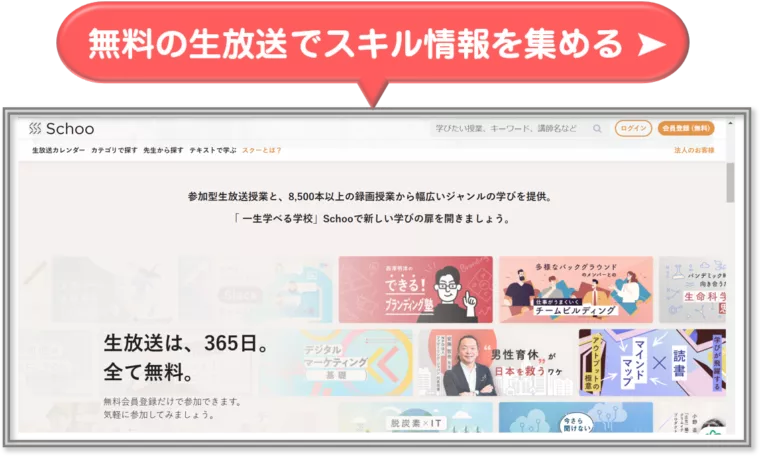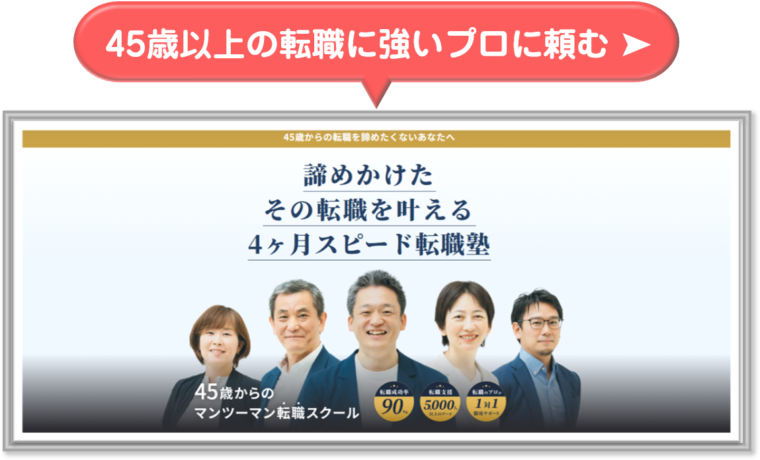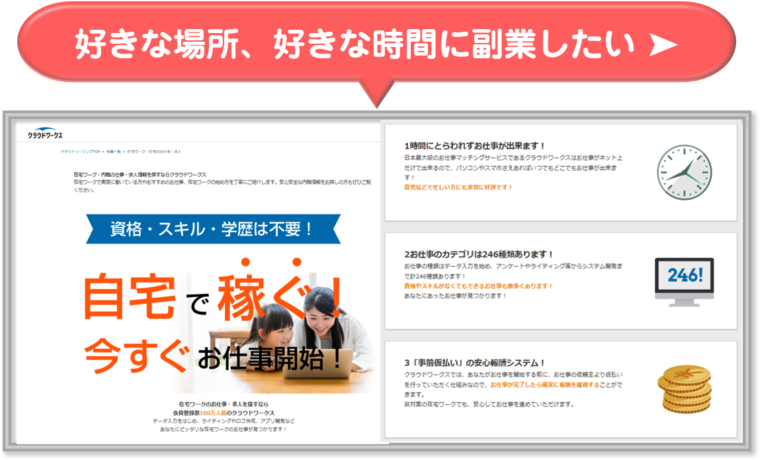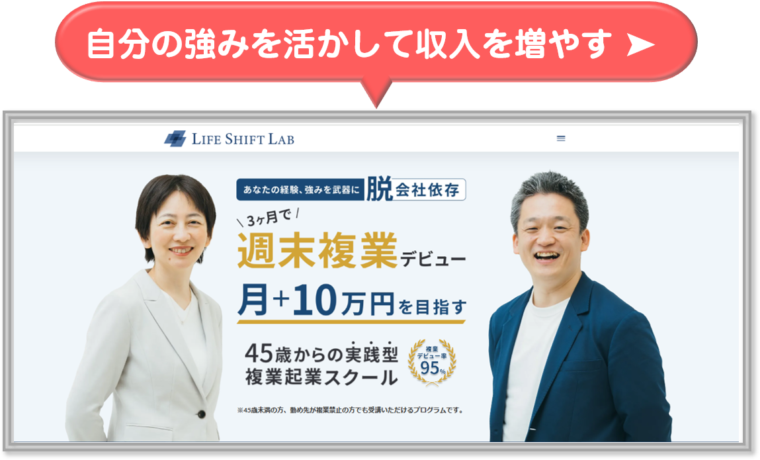私たちは説明の場に立つとき、
何を話すかは意識して考えるが、どう話すかについては準備がおろそかになりがちです。
それは、だれもが自分の話し方はごく自然だと考えているからです。
しかし、筆者は、社員の評価が、その人の「話し方」に左右されるケースを多く見てきました。
話し方は、いわば「自分の見せ方」
話し方によっては、自信に欠ける、強引な印象など、マイナスイメージを相手に与えます。
そこで本記事では…
「話し方」の影響力を解説!
2回に分けて記事にします。
- 高い評価を得る(話し方の)習慣
- 評価を下げる話し方の習慣
※ 本記事は❶にあたります。
簡単に内容を知りたい方は Instagramへどうぞ…
https://www.instagram.com/mitsuya_biz
話し方の影響力
仕事でのプレゼンテーション、友人との会話、家族とのやり取りなど、話し方は相手に与える印象だけでなく、事の成り行きにも大きく影響します。
しかし、私たちはだれもが自分の話し方はごく自然だと考えている。
あなたの評価に大きな影響を及ぼしているのは、この認識の差です。
大切なことは…
話し方の影響力を理解して
その習慣を改善すること
高い評価を得ている人の、話し方の習慣とは…

❶ 進行を促す話し方、要点を整理する話し方ができる

アイデアを出す人よりも…
- 会議の中で、進行を促す発言をする
- 要点を整理したりする
人のほうが、貢献度が高いと評価される。
アイデアを比較したり関連づけたりして結論に導く役割を果たす人は、終始会議に影響力を及ぼしてるなど、キーパーソンと見なされます。
具体的には以下のような話し方…
- 比較の観点を定めて
「では、…の点で比較するとどうなるだろう?」
など新たな見方を提案するような話し方 - 「メリットとしては…・デメリットとしては…」
など項目を設定して整理を促すような話し方
たとえば…
では、AのアイデアとBのアイデア
それぞれ収益性という点で比較すると
どうなるだろう?
A商品のカテゴリーには
マーケットリーダーがないことがデータからわかります。
メリットとしては 一気にシェアを獲得できる可能性が高いことです。
デメリットとしては…
というように…
進行に関わる話し方や、要点をまとめるような話し方ができる人は、高い評価を得ます。
ただし、言い出すタイミングがずれたり、指摘する内容が未熟であったりすると、逆効果。
ポイントは…
適切なタイミングや新たな視点を考えながらミーテイングに臨む習慣
キャリアップのための
必須の習慣です。
❷ 適切なフィードバックができる

相手や状況を踏まえてフィードバックできる人は、「この人の話は聞くに値する」という印象を相手に与え、信頼とともに高い評価を得る。
ただし、前述同じように、未熟な場合は低評価になります。
だからこそ習慣化し、高めていく努力が必要。
これを若いうちから意識して実践する人と、無関心な人とでは大きな差が生まれます。
具体的には…
次の❶~➎の観点で習慣化しましょう。
具体的な場面や内容を取り上げるようにします。
漠然とした感想や印象を述べるだけでは、次回より、あなたからのフィードバックは期待されなくなります。
どんな場面のどんな言動、事前準備や資料などが、成果にどのように機能したか、というように、具体性をもったフィードバックをします。
❶を踏まえて、具体的な改善点を2~3程度に整理します。
総括的な分析を併せて示すと、さらにフィードバックの信用度が高まります。
ポイントは過程の観察です。
プレゼンを例にとると、提案中の受け手の反応をよく観察する、などです。また、プレゼン後にどんな内容の質問が多く出されたか、なども改善点を整理する上で参考になります。
場に応じたフィードバックが大切だということです。
例えば、プレゼンに対して多くの賞賛を得た状況においては肯定的なフィードバック。逆に、次回を期す場合は、具体的な改善点を返す、など場面や状況に応じてフィードバックします。
俗にいう空気を読む、ということです。
否定的なフィードバックを厭う人が多い、ということも念頭に入れておきます。
人は「ほめてほしい」「成果を認めてほしい」という気持ちが先立つ傾向にあります。逆に、相手が、「具体的な改善点を求める」人、「的確な指摘をすることよって信頼を得られる」人であれば、フィードバックの質に留意します。
相手が上司か部下かなど、立場の違いも考慮します。
❸❹を踏まえて、「肯定的なフィードバック」と「改善を促すフィードバック」を、どの順序で構成するか、を明確にします。
特に、相手意識が重要です。日ごろからフィードバックする相手をよく観察してください。
一般的に、企業のトップの方は、「なるほど」と思わせる改善点を指摘されるのを好みます。トップは、常に「業績を伸ばす変数は何か」ということを求めているからです。
新入社員に対しては、耐性の問題がありますので、個に応じたフィードバックを心がけてください。
肯定的なフィードバック(社内プレゼン・対上司)の具体例としては…
同じカテゴリーの株価変動のデータと関連づけて、収益の見通しを説明したときに、幹部の皆さん、目の色が変わりましたね。
うなずく幹部も複数いました。
資料のマッチングが成功に結びついたのだと思います。
現在、うちは冒険できませんから、確実性をアピールしたことが、説得力を高めたんでしょう…
ミーティングで、関連する多くのデータの中から、効果的な材料をチームで検討したことがよかったんですかね…
このように、観察をとおして、具体的な場面を示して根拠を述べます。
そして、自分の分析を加える。
さらに
- 確実性をアピールしたことが、説得力を高めた。
- ミーティングで、関連する多くのデータの中から、説得に有効なものをチームで検討した。
など、総括的な分析を述べます。
なお、上司によっては、部下のしゃべりすぎを嫌う人もいるかもしれません。
その場合は、会話の中で、少しずつ自分の分析を述べましょう。
大切なことは、日ごろから…
相手の志向にアンテナを張っておくこと
改善点を指摘する場合は…
「…がいけなかった」ではなく
「…すると次回はうまくいく」
という話し方を心がけましょう
高い評価を得る「話し方」は、ビジネスパーソンが習慣化すべきスキル

キャリアアップのために、「特定のスキルを、特定の期間学習する」というイメージで取り組んでも、なかなか身につきません。
大切なことは、習慣化。
高い評価を得る「話し方」は、習慣化すべきスキルの一つ。
「あいつはできる」と周囲に思わせる話し方を探求し、習慣化すると…
あなたの望むキャリアは
手に入ります。
営業にかかわる方は、「営業コミュ力」について解説している記事があります。
必要に応じてご活用ください。
「話し方」が直接評価につながる場がスピーチ。
以下の記事で、スピーチの上達について解説しています。ご参照ください…
次回は…
「評価を下げる(話し方の)習慣」をテーマに解説。
本記事の関連書籍を紹介します…
忙しいあなたも、耳は意外とヒマしてます。
時間がない人におススメなのは audiobook!
ビジネスパーソンの主流は、耳読書。
読書効率がグンと上がります…
今後の生活資金に対する不安、健康不安、急な出費への備え…
そんな不安を安心に変える方法を記事にしました。
キャリアアップを目指しながら副収入もほしい…という人向けの記事です。