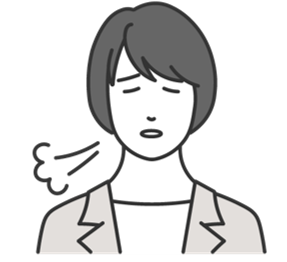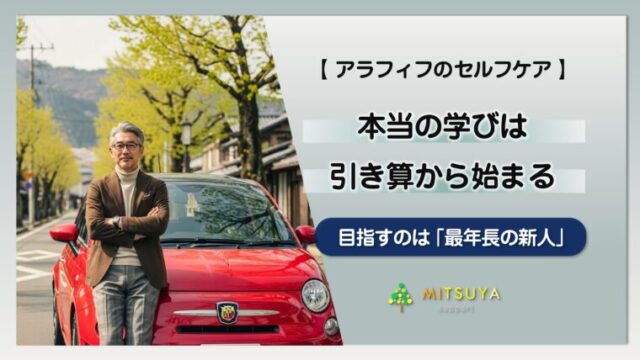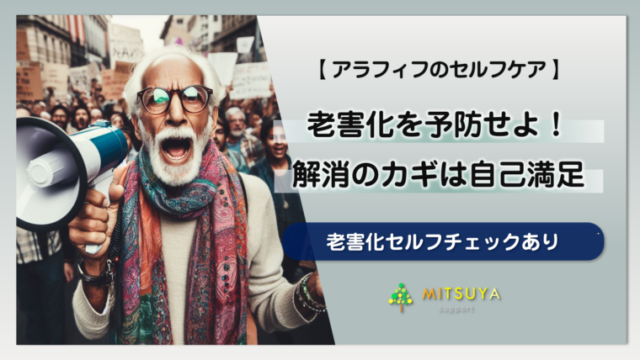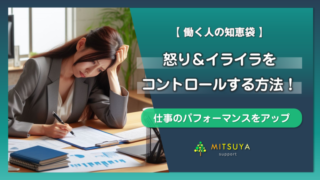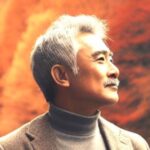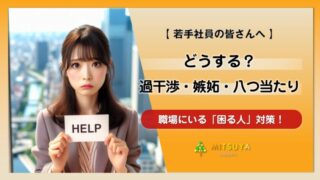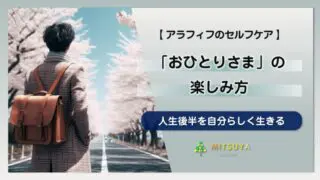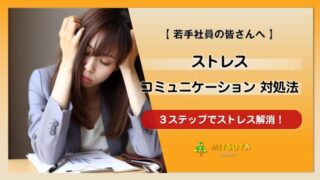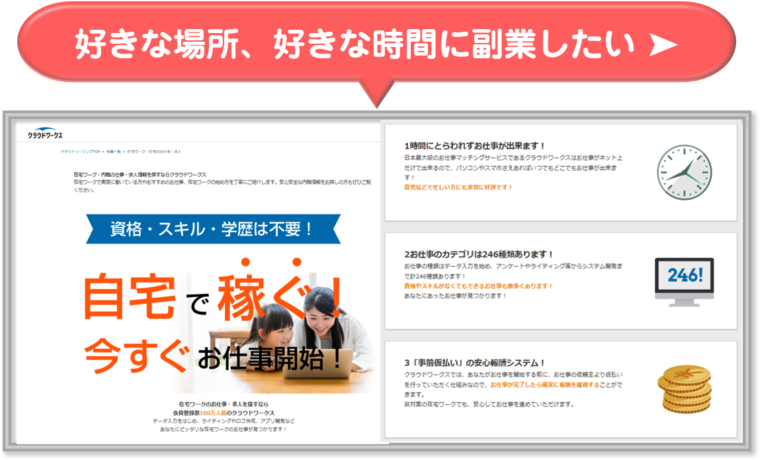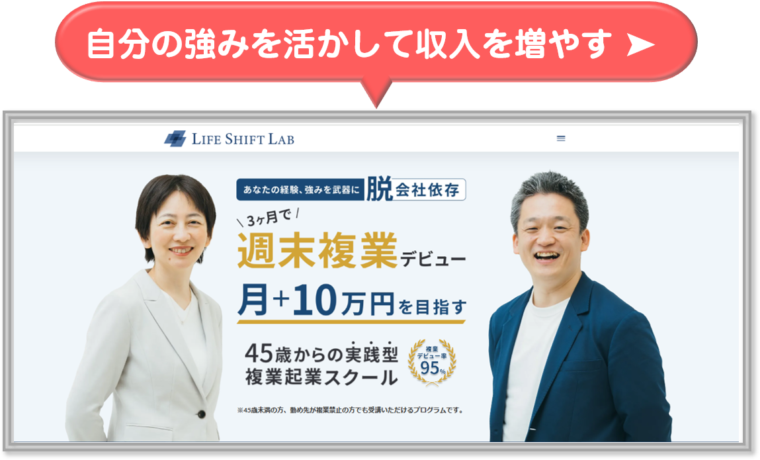大人のためのライフスキル!:毎日を充実させる3つの幸福度アップの秘訣

仕事に追われる人生、
もっと自分らしく生きたい…
確かに…
現代社会では「自分らしく」過ごすこと自体が贅沢に感じるかもしれません。
誰かの期待に応え続ける毎日では、「自分の時間」を見失いやすいからです。
そこでこの記事では…
「なんとなく」過ぎる毎日を、「自分らしく」過ごせる時間に変えるヒントをご紹介します。
その秘訣は、次の3つのポイントにあります。
- 秘訣 その1 「私のルーティン」をつくる
一流は、習慣の力で自分の時間をつくる - 秘訣 その2 「フロー状態」をつくる
没頭の先にある「フロー体験」が深い満足感を生む - 秘訣 その3 「ぼんやり」をつくる
脳のメンテナンスには「ぼんやり時間」が必要

秘訣 その1 「私のルーティン」をつくる

なぜ、人の習慣は真似しても続かない?
誰かの真似をしてみたが、なぜか続かない…
そんな経験は、誰にでもあると思います。
たとえば「瞑想がいい」と聞いて始めたけれど、
すぐに挫折してしまった…
それはあなたの意志が弱いからではありません。
生活習慣というのは、自分の意志だけでなく、自身の生活環境や体調、時間の使い方にも深く関わるものです。
したがって…
理想的なルーティンは「自分に合う形」を、試行錯誤しながらつくる必要があります。
たとえば、小説家・村上春樹氏…
創作に集中するため、次のようなルーティンを自ら築き上げました。

出典:”The daily routines of famous creative people”
https://podio.com/site/creative-routines
このルーティンも、最初から完成されていたわけではなく、試行錯誤の末に「自分に合った形」へと落ち着いたものだそうです。
ルーティンが不安を減らす
先のことがよく分からない時代だからこそ、日々の暮らしに「この時間はこれをやる」という決まった流れ(ルーティン)をつくるのが、心の安定を守る強い味方になります。
2022年にNatureに掲載された論文「Effects of predictable behavioral patterns on anxiety dynamics」では…
(この研究結果は)感情の安定性を維持するための行動予測可能性の重要性を強調し、規則的なルーティンを促進することが不安障害に対する有望な介入となる可能性があることを示唆している。
These findings underscore the importance of behavioral predictability for maintaining affective stability and suggest that promoting regular routines may be a promising intervention for anxiety disorders.
https://www.nature.com/articles/s41598-022-23885-4
こうした「自分で決めた流れ=ルーティン」をもつことは、生活に予測性とリズムを与え、時間に対するコントロール感(perceived control over time)を育てることにつながります。
心理学の研究(Adams et al., 2019)では…
時間の主導権を握っていると感じる人ほど、ワークライフバランスが整いやすく、ストレスが減り、精神的な幸福感が高まる
When individuals feel in control of their time, they are better able to manage competing demands between work and family, leading to greater well-being.
— Adams, G. A., Kniest, T., Brabson, L. A., & Prunier, S. G. (2019). Relationships among perceived control over time, work–family conflict, and well-being. Journal of Occupational Health Psychology, 24(1), 15–28.
…と報告されています。
つまり…
ルーティンは「生活を縛るもの」ではなく、「自分の時間を取り戻すための仕組み」なのです。
自分の時間をつくるメリット
「時間がない」と感じたら、「自分の時間をつくる」ことに意識を向けましょう。
これが創造性や集中力を高めるカギとなります。
たとえば、ソフトバンク創業者の孫正義氏…
若い頃から「1日15分の発明時間」を自分に課していました。
この15分を区切り、問題解決型発想法、逆転発想法、複合連結法といった思考法を駆使して、毎日アイデアを生み出していた。
一見短いようでいて、目的をもって使えば深く集中できる時間。
彼にとってこの習慣は、起業家としての創造力や判断力を育てる土台になりました。
他にも、星野リゾートの代表・星野佳路氏は…
1日15,000歩の散歩を日課にしています。
歩きながら考えることで、デスクでは浮かばないアイデアが自然と湧いてくるといいます。
共通しているのは、時間が「空く」のを待つのではなく、自ら「つくっている」ということ。
理想の時間の使い方は、最初から見つかるものではありません。
試して、合わなければ変えて、自分なりのリズムをつくっていくものです。
時間をつくれば、発想も気づきも自然と生まれる。
まずは、「自分のための時間」を意識して確保するところから始めてみましょう。
小さな一歩が、あなたの未来を大きく変えるかもしれません。
秘訣 その2 「フロー状態」をつくる

いい結果が出ても満足しない理由
昇進した、資格に合格した、大きな成果をあげた…
しかし、
不思議と心は満たされない
こんな経験、ありませんか?
結果の喜びはつかの間。
深い充実感は、「成果」ではなく「過程」に宿ります。
このことを、心理学者チクセントミハイは「フロー」と呼びます。
フローとは、何かに完全に集中し、流れに乗って没頭している状態のこと。
人はフロー状態、すなわち何かに完全に集中し、流れに乗っている過程そのものから、深い満足感や幸福感を得る。
The Pursuit of Happiness
https://www.pursuit-of-happiness.org/history-of-happiness/mihaly-csikszentmihalyi/
つまり…
人が感じる深い充実感は、「達成そのもの」ではなく、「没頭しているプロセス」にあるのです。
フローは「幸せな大人」のためのライフスキル
フローは、スポーツに没頭しているときや、音楽に夢中になっているとき、ものづくりや読書に集中しているとき…
誰もが一度は体験したことのある…
あの「夢中の時間」です
そしてこの「夢中の時間」こそが、「結果」を超えた満足感をもたらします。
Peiferら(2014)の研究では、
ストレスのある状況でもフロー状態に入ると、ストレスホルモン(コルチゾール)の分泌が抑えられる
…ことがわかっています。
また、フロー中は脳の集中力や注意力が効率的に使われるという報告もあります。
Peifer, C., et al. (2014). The relation of flow-experience and physiological arousal under stress—Can u shape it? Journal of Experimental Social Psychology, 53, 62-69.
さらに、Nakamura & Csikszentmihalyi(2002)は、
フローをよく体験する人ほど幸福感や自己効力感が高く、仕事や人間関係にも良い影響をもたらす
Nakamura, J., & Csikszentmihalyi, M. (2002). The concept of flow. In C. R. Snyder & S. J. Lopez (Eds.), Handbook of positive psychology (pp. 89-105). Oxford University Press.
…ことがわかっています。
つまり、「フローを日常に生み出す」ことは、現代を生きる大人にとって極めて有効なライフスキルなのです。
毎日にフローを取り込む2つの習慣
では、どうすればそのフロー状態を、意図的に日常へ取り込めるのでしょうか?
毎日にフローを取り込む2つの習慣を紹介します。
自分で時間制限を設ける(タイムプレッシャー)
時間を区切って集中することで、フローに入りやすくなります。
前述の…
ソフトバンク創業者・孫正義氏の「1日15分の発明時間」がそれにあたります。
ここで重要なのは、
他人に課される締め切りではなく…
「自分で決める」〆切のこと
自発的なプレッシャーは、ストレスではなく集中力を引き出します。
自分で締め切りを設定することで、集中し、効率的に物事に取り組める環境をつくることができる。それが、集中力とモチベーションをさらに引き出す。
By setting deadlines for yourself, you create a structured environment that encourages focus and efficiency. When you set a deadline for yourself, it ignites a sense of urgency that can enhance focus and motivation
https://focuskeeper.co/glossary/what-is-self-imposed-time-limits
小さな進行感にこだわる
日々の活動の中で「昨日より少し前に進めた」「何かが上達した」と感じられる…
そんな「小さな進行感」が、私たちにとって大きなやりがいとなり…
フローに向かう第一歩となります
これは、人間が本来もっている「成長したい」「何かを習得したい」という有能感の欲求が関係します。
この欲求が満たされると、心理的に満足感が生まれ、外からの報酬がなくても自然とやる気が湧いてくるのです。
心理学ではこの状態を「内発的動機づけ」と呼び、モチベーションを高めるカギとされています。
そしてこの内発的なやる気こそが、自然とフロー状態へ入るための重要なきっかけになるのです。
進行感については、以下の記事でも詳しく解説しています。ご活用ください。
秘訣 その3 「ぼんやり」をつくる


ひらめきと「ぼんやり」の関係
考えても答えが出ないとき、ふとした瞬間に
アイデアが浮んだ!
実は、そのひらめきには「ぼんやり」が関係しています。
この「ぼんやり」とした何もしない時間にこそ、脳は裏側で静かに働いているのです。
心理学者のダニエル・カーネマンは、これを「システム1」と「システム2」で説明しました。
- システム1
直感的で素早く、自動的・無意識的に働く思考 - システム2
論理的で時間をかけて意識的に考える思考
私たちの日常の行動の多くは、システム1による自動的な判断によるものです。
複雑な問題や新しい課題に直面したときにはシステム2を使う。
私たちはつい、考える=システム2を重視しがちですが、創造的な「ひらめき」は、必ずしも集中して考えているときに生まれるわけではありません。
脳科学の研究によると、リラックスしてぼんやりしているとき(たとえば散歩中やシャワーを浴びているときなど)にも、創造的なアイデアが生まれやすいことがわかっています。
誰もが一度は経験したことのある
「あの気づきの瞬間」です
前述の
星野リゾートの代表・星野佳路氏の「1日15,000歩の散歩」がコレにあたります。
科学が証明 「ぼんやり」の力
ムダに思える「ぼんやり」とした時間。
この無意識の時間こそが、「努力」では届かない発見をもたらします。
Schoolerら(2011)の論文では…
マインドワンダリング(心のさまよい)は創造的な問題解決やひらめきを促進する可能性がある。
…ことが示唆されています。
実際に、マインドワンダリング中に創造的なアイデアが生まれやすいことを示す実験的な知見が報告されています(Baird et al., 2012 など)。
つまり、意識が外界から離れて自由にさまよう時間が、創造性の発揮に役立つと考えられています。
DMNを活性化させる
ぼんやりしているとき…
私たちの脳ではデフォルトモードネットワーク(DMN)と呼ばれる領域が活性化します。
このDMNは…
自己の内省や過去の記憶の振り返り、未来の計画、さらには創造的思考に深く関与していることが、近年の脳科学研究で明らかになりました。
Raichle, M. E. (2015). The brain’s default mode network. Annual Review of Neuroscience, 38, 433–447.
脳科学者の茂木健一郎氏も、DMNの重要性から、毎朝1時間のランニングのほか、移動時間は意識して歩くようにしているとのこと。
氏はDMNの効用を、次のように述べています。
公園の緑の中を歩くと、「あの人の言った意味はこういうことだったのか」「自分の心はこういう感情にあったのだな」といったことが、思うともなく整理されていくのだから面白いことです。
出典『山中教授の自分を変える練習』悩みとストレスを消す練習より
注意点は…
DMNが過度に活性化すると、注意力が散漫になったり、不安感が増したりすることです。
DMNの活性化と非活性化のバランスを適切に保つことが大切。
つまりポイントは…
一日のなかに、フロー状態とDMNが働く時間の両方を、バランスよく設けること
では、どうすればその「ぼんやり時間」を、意識的に日常へ取り込めるのでしょうか?
「ぼんやり」を取り込む2つの習慣
毎日に「ぼんやり」を取り込む2つの習慣を紹介!
思考を手放す時間を日常に差し込む(マインド・オフ)
スマホを手放し、あえて「考えない時間」をつくってみましょう。
たとえば…
- 電車に揺られているとき
- カフェでひと息つくとき
- ベランダで空を眺めるとき
ただ何もせず、景色や音にぼんやりと意識を向けるだけでOKです。
哲学者アラン・ド・ボトン曰く…
何もしない時間こそ
現代人にとって最も贅沢な時間
ここで大事なのは…
「頭を休ませよう」と頑張らないこと
ただ「思考を手放す」だけで、脳は自然に情報を整理しはじめます。
脳科学の研究でも、こうした意識的な「マインド・オフ」によって、内省力や創造性が高まることが分かっています。
忙しい毎日の中に、あえて空白をつくる。
その小さなゆるみが、心に静かな満足感を育ててくれます。
日常に「単純作業」を取り入れる
洗い物やアイロンがけ、植物の水やり…
単純で繰り返しの作業は、思考のノイズを静かに整えてくれます。
この「何気ない時間」こそが、心をゆるめ、自分自身と静かに向き合える貴重な時間です。
たとえば…
- 気づけば悩みが少し軽くなっていた
- 昔の言葉がふと思い出され、心がほぐれた
- 前より穏やかに物事を受け止められるようになった
こうした小さな内面の変化が、日常に落ち着きと充実感をもたらします。
心理学者ジョナサン・スクーラー曰く…
「マインドワンダリング(意識がさまよう状態)」は、
脳が次の自分に向けて
準備をしている時間です
“Mind-wandering is not a failure of attention, but the mind preparing for its next leap.”― Jonathan Schooler
つまり、「ただ手を動かしているだけ」のように見える時間が、実は心の奥で整理や再構築を進めているのです。
この小さな「整える習慣」が、あなたの毎日に穏やかな満足感を育ててくれます。
「なんとなく」の毎日に、3つの小さな変化を


気づけば、
今日もなんとなく終わっていた…
そんな毎日を変えたいなら、「何を成し遂げるか」より「どう過ごすか」に目を向けてみましょう。
この記事では、大人のための3つの「幸福度アップ習慣」をご紹介しました。
1|「私のルーティン」をつくる
誰かの真似ではなく、自分の生活リズムに合ったルーティンをつくることで、心に安心感と予測可能性が生まれます。
自分の時間を自分で設計することで、充実感はぐっと高まっていきます。
2|「フロー状態」に入る
何かに夢中になって没頭している…
そんな状態が「フロー」です。
結果を追うのではなく、今この瞬間の「過程」に意識を向けることが、持続する幸福感につながります。
3|「ぼんやり」を取り入れる
意識的に何もしない時間。
洗い物や散歩、空を眺めるひとときに、脳は静かに整理を始めます。
こうした「内なるゆるみ」が、心の余白を生み、日々に落ち着きを与えてくれます。
3つに共通するのは…
自分自身との向き合い方を変えること
小さな習慣を積み重ねることで、あなたの毎日は、穏やかで満足感のある日々が、少しずつ増えていきます。
本記事の関連でおススメする書籍は…
「グッド・ライフ 幸せになるのに、遅すぎることはない」
何が幸福な人生に影響を与えるのか、教えてくれます!
忙しいあなたも、耳は意外とヒマしてます。
時間がない人におススメなのは audiobook!
ビジネスパーソンの主流は、耳読書。
読書効率がグンと上がります…